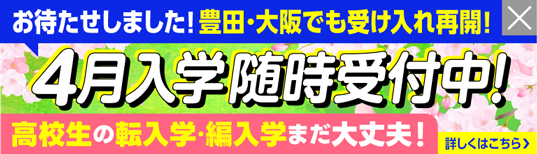タバッコ峠...なんとも不思議な名前(その4)
2017年10月23日
タバッコ峠...なんとも不思議な名前(その4)
さて、最終回。
いよいよタバッコ峠へ GO!! です。 w

空はいつの間にか羊雲?
爽やかな景色です。
途中の景色を堪能しつつや、「十郎沢」「栃原新田」などという地名に山間の農村の歴史を感じながら車を走らせていると...

あっという間にあと100m。

どうやら ↓ ここらしい。

ここから常陸大宮市 ↑ と反対側に廻るとここから大子町 ↓ と、市境を示す標識。
右手に石の標識があるのが分かりますか?

「享和元年」と読んいいのでしょうか。
...だとすると、この道標が建てられたのは1801年江戸の後期になりますかねぇ。

美和村(現常陸大宮市)の方から、北上すると栃原村、さらに東に進むと大澤村(現在の大子町大沢)に至ることが刻まれています。
タバッコ峠その由来については、web上には次のようなものがありましたので、紹介しておきます。
1.タバッコの由来 ...縄文語説
鈴木健氏の『日本語になった縄文語』によると、峠のことをタオ、ター、タワなどというところが多くあり、taorは低い所を意味し、山の鞍部などを指す言葉であり、撓む(タワム)やタワワに実るなどの言葉と同義語であるとしています。この元アイヌ語の峠を表す言葉が残ったと考えるのが妥当でしょう。(http://www.rekishinosato.com/suwajinjya.htm)
2.タバッコの由来 ...アイヌ語説①
有力説は、アイヌ語で、タバは地形を指す言葉で峠の事。コは愛称を示す接尾語。 「たわみ → 山のたわんだところ → たわっこ → タバッコ 」であろう。(http://blog.goo.ne.jp/komagata1860/e/fad96aceb4cdd2a03c83d7ec05423a17)
タバッコの由来 ...アイヌ語説②: ↑ ①の「たわむ」の語幹「たわ」「たば」(山の鞍部)+「こ(愛称)」説に異論を唱えるものもあります。
享和元年(1801)の道標には「はとう(馬頭)からすやま(烏山)とりのこみち(鷲子道)」 とあり、大沢川最奥の集落と緒川流域を結ぶというよりも、久隆川流域(旧道)と那珂川本流、奥州街道を結ぶ意味合いが大きかったのではないだろうか。 旧道の最高点からタバッコ峠に下り、そこから尾根伝いに尺丈山(511m茨城栃木県境) 鷲子山(463m茨城栃木県境)の尾根を通り鷲子山神社、馬頭町烏山町に到る。 道標からすれば、タバッコ峠は尾根への入り口であって「山の鞍部」の意味ではない。 (「アイヌ語地名の南限は?」https://academy6.5ch.net/test/read.cgi/geo/1111743396/l50)
タバッコの由来 ...アイヌ語説③: また、↓ の『奥久慈・大子町の地名』(菊池国夫)によれば、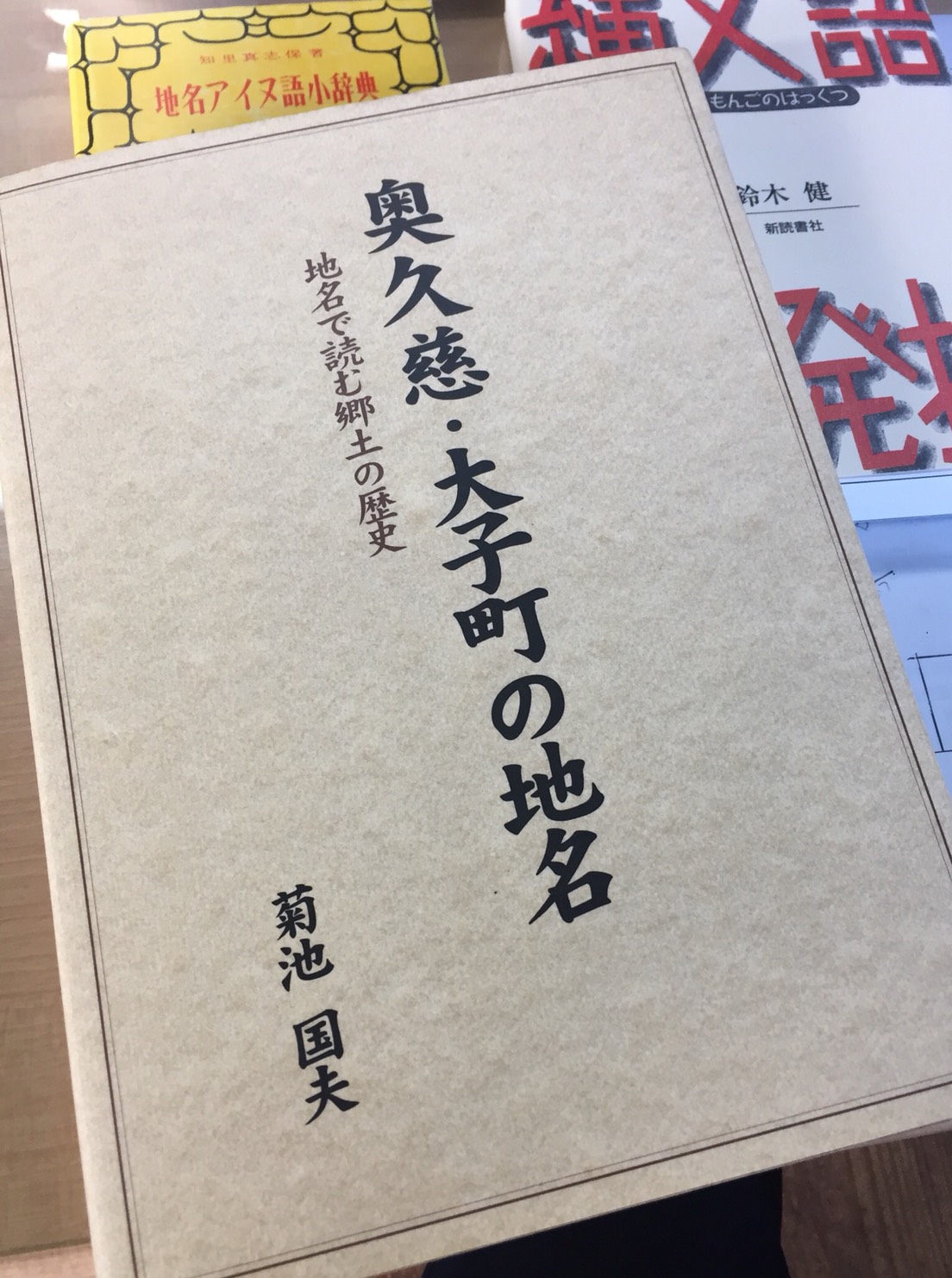
・16世紀になって「煙草」が日本へ入ってからはわずかな時間しか経っていない(ので、ここからの由来は考えづらい)。
・400年以前などは、(ここが)常陸の国と陸奥の国の異郷の国境でもあったろう。ta-pak-noタパクノ[ここまで]の感覚は、とうじの生活圏の中では極めて現実的なものではなかったろうか。
とあります。
※ 『地名アイヌ語小辞典』(知里真志保)を見てみると、「tapkop,-i」 たプコプ ②尾根の先にたんこぶのように高まっている所。[ < tap-ka-o-p 肩・の上・にある・もの ? ] とあります。
...このアイヌ語説③に従い「タバッコ峠」が境だとすると、大子町は昔は陸奥の国に属していたということになるのかな?
...アイヌ語かぁ。
『奥久慈・大子町の地名』には、栃原の地名だけでも「タバッコ」のほかに「カッタイジャリ」「ヒチョメキ」「ヒラミタ」「ボタラ」などの不思議な地名が紹介されています。
なんだか、大子町をもっと調べたくなる「タバッコ峠」探訪になりました。
以上、長々と大変失礼いたしました。
この記事の「学校・キャンパス」のページを見る
この記事の関連カテゴリー