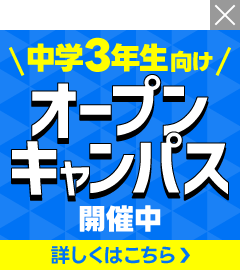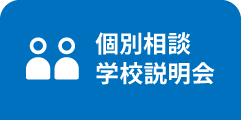- 通信制高校のルネサンス高校グループ
- ブログ
- 名画「落穂拾い」!?
名画「落穂拾い」!?
ルネサンス高等学校
名画「落穂拾い」!?
2021-05-28
かのフランスの画家ジャン=フランソワ・ミレーによって1857年に描かれた油彩作品「落穂拾い」を彷彿とさせるこの光景。

ここのところ、梅雨入りしたかと思うくらい雨が続いています。↓ は昨日の風景です。

なので、ルネ茶もスクスク(^▽^)/、グランドの芝生の中に雑草もスクスク(TдT)エーン! です。

で、読書の町宣言をしている大子町の「朝の10分間読書」ならぬ
ルネ高の「朝の10分間草むしり」です。
...早く、スクーリングが再開できるのを願いつつ。
因みに、Wikipediaによれば、ミレーの「落穂ひろい」のテーマは、旧約聖書「ルツ記」によるとのことです。
「ルツ記」によれば、未亡人となったルツが義母のナオミを養うために、裕福な遠縁の親戚ボアズの畑で落穂拾いをする。ボアズは姑につくすルツに好意をもっていた。この姑ナオミのおかげで、ルツとボアズは結ばれ、ダヴィデの祖先となったとのことです。
そして、旧約聖書「レビ記」19章9節から10節に定められた律法に、「穀物を収穫するときは、畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。...これらは貧しい者や寄留者のために残しておかねばならない。」、「レビ記」23章22節には「畑から穀物を刈り取るときは、その畑の隅まで刈り尽くしてはならない。収穫後の落ち穂を拾い集めてはならない。貧しい者や寄留者のために残しておきなさい。」、「申命記」24章19節には「畑で穀物を刈り入れるとき、一束畑に忘れても、取りに戻ってはならない。それは寄留者、孤児、寡婦のものとしなさい。」とあり、落穂ひろいは、近代の農村社会でも貧者の権利として一部に残っていた慣習であったとのことが記されてあります。
上の話を読みながらブラウジングしてたら、web上にこんな記事を発見
なんだか話がSDGsまで広がりそうな、朝の10分間草むしりでありました。


デジタルパンフレット
学校案内パンフレットを今すぐWebでチェック!