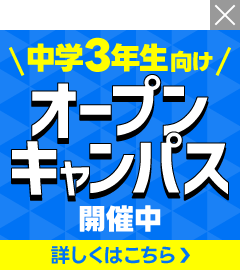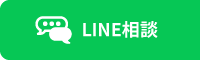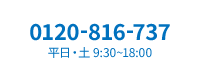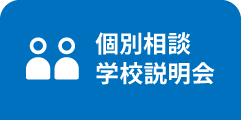ブログ
- 全て
- ルネサンス高等学校
- ルネサンス豊田高等学校
- ルネサンス大阪高等学校
場所で絞り込む
ジャンルで絞り込む
年度別で絞り込む
場所で絞り込む
ジャンルで絞り込む
年度別で絞り込む
場所で絞り込む
ジャンルで絞り込む
年度別で絞り込む
場所で絞り込む
ジャンルで絞り込む
年度別で絞り込む
 (1)-thumb-346xauto-27120.jpg)
2025-05-12
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】大阪・関西万博「JAPAN EXPO Paris in Osaka 2025」に出展いたしました!
みなさん、こんにちは梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です!先月、eスポーツコースでは4月26日か…

2025-05-02
ルネサンス高等学校
【池袋キャンパス】5/11(日)オープンキャンパス開催!
こんにちは。池袋キャンパス担当です! 今月から2026年度入学検討者のオープンキャンパスを開催します…

2025-04-25
ルネサンス高等学校
【池袋】2025年度も池袋キャンパスをよろしくお願いいたします!
こんにちは~池袋キャンパス担当です! eスポーツコース池袋キャンパスの新年度がスタートし早一か月!…

2025-04-25
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】今年度初開催★ 5月25日オープンキャンパスご予約受付中
こんにちは梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です!皆さま、いかがお過ごしでしょうか? 新年度…

2025-04-22
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】eスポーツコース新入生オリエンテーションを開催【2025年度】
こんにちは~梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です!春とともに、新しい出会いの季節 がやってきまし…

2025-04-18
ルネサンス高等学校
【横浜】2025年度新入生講義スタート!eスポーツコース新入生初日レポートー新入生向けイベントも実施!
★1・2限:オリエンテーション&アイスブレイク 午前中はオリエンテーションからスタート。職員の自己紹…

2025-05-02
ルネサンス高等学校
【池袋キャンパス】5/11(日)オープンキャンパス開催!
こんにちは。池袋キャンパス担当です! 今月から2026年度入学検討者のオープンキャンパスを開催します…

2025-04-25
ルネサンス高等学校
【池袋】2025年度も池袋キャンパスをよろしくお願いいたします!
こんにちは~池袋キャンパス担当です! eスポーツコース池袋キャンパスの新年度がスタートし早一か月!…

2025-04-18
ルネサンス高等学校
【横浜】2025年度新入生講義スタート!eスポーツコース新入生初日レポートー新入生向けイベントも実施!
★1・2限:オリエンテーション&アイスブレイク 午前中はオリエンテーションからスタート。職員の自己紹…

2025-04-08
ルネサンス高等学校
【岡山】eスポーツキャラバン in OKAYAMA 報告!
3月20日(木)に岡山キャンパスにて、『eスポーツキャラバン in OKAYAMA』 を実施いたしま…

2025-04-15
ルネサンス豊田高等学校
【名古屋】eスポーツコース 新入生オリエンテーション開催
こんにちは!名古屋eスポーツキャンパス担当です! 名古屋eスポーツキャンパスでは、4月12日(土)に…

2025-02-10
ルネサンス豊田高等学校
【豊田駅前キャンパス】カップケーキを作ろう!!イベントを実施しました!!
みなさん、こんにちは!! ルネサンス豊田高校では、生徒交流のためのイベントを毎月実施しております♪ …

2025-01-24
ルネサンス豊田高等学校
【豊田スカイホール】バドミントンをしよう!!イベントを実施しました!!
みなさん、こんにちは!! ルネサンス豊田高校では、生徒交流のためのイベントを毎月実施しております♪ …

2024-12-25
ルネサンス豊田高等学校
【名古屋】Riot Games One 2024 DAY2に参加!
こんにちは☺︎名古屋eスポーツキャンパス担当です! 先日、ステージゼロ2024【ヴァロラント部門】で…

2024-12-20
ルネサンス豊田高等学校
【名古屋栄キャンパス】クリスマスパーティを実施しました!!
みなさん、こんにちは!! ルネサンス豊田高校では、生徒交流のためのイベントを毎月実施しております♪ …
 (1)-thumb-346xauto-27120.jpg)
2025-05-12
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】大阪・関西万博「JAPAN EXPO Paris in Osaka 2025」に出展いたしました!
みなさん、こんにちは梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です!先月、eスポーツコースでは4月26日か…

2025-04-25
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】今年度初開催★ 5月25日オープンキャンパスご予約受付中
こんにちは梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です!皆さま、いかがお過ごしでしょうか? 新年度…

2025-04-22
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】eスポーツコース新入生オリエンテーションを開催【2025年度】
こんにちは~梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です!春とともに、新しい出会いの季節 がやってきまし…

2025-03-21
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】卒業おめでとう!【eスポーツコース 】
みなさん、こんにちは梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です! 3月7日(金)ルネサンス大阪高等学校…

2025-02-17
ルネサンス大阪高等学校
【梅田・なんば】今年度最後のオープンキャンパス開催/一般入試2期エントリーまもなく開始 ♪
みなさん、こんにちは梅田・なんばeスポーツキャンパス担当です! 気づけばもう2月...今年度の登校も…

2025-01-15
ルネサンス大阪高等学校
【ルネ中等部】大阪市在住の方必見★月1万円の費用を助成!
こんにちは!ルネ中等部です。ルネ中等部では、2025年1月より大阪市在住の中学生を対象とした【大阪市…