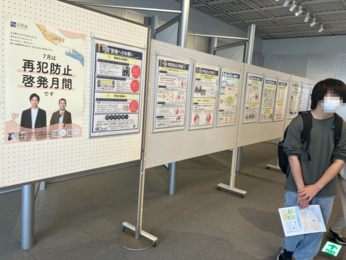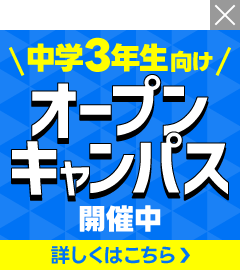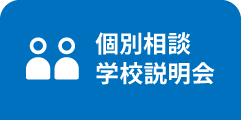- 通信制高校のルネサンス高校グループ
- ブログ
- 教育ボドゲ12 ケン・ロビンソンの素質と才能の考え方とボードゲーム
教育ボドゲ12 ケン・ロビンソンの素質と才能の考え方とボードゲーム
ルネサンス高等学校
教育ボドゲ12 ケン・ロビンソンの素質と才能の考え方とボードゲーム
2018-02-17
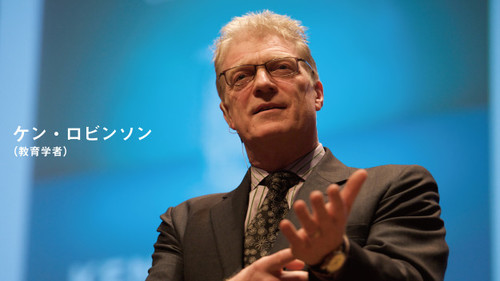 2006年のTEDトークで、ケン・ロビンソンの教育に関するトピックが話題になってから10年以上が過ぎました。
2006年のTEDトークで、ケン・ロビンソンの教育に関するトピックが話題になってから10年以上が過ぎました。
・「学校教育は創造性を殺してしまっている」
・「教育の死の谷を脱するには」
・「教育に革命を」
の3つのトークの中で、いずれも共通するテーマは「子どもの可能性」に言及し、特に従来型の教育では、ある一定の層の子どもたちが、自分たちの可能性を切り開くのをむしろ邪魔してしまうというものです。
学校では教科書を使った読み書きを基準に教えるなか、じっとしていられない生徒は「できの悪い子」として認定されてしまいます。一方で、そうした子が別の分野で花開いたという経験もあります。ケン・ロビンソンは、芸術分野(ダンス)で特別な才能の子どもが成功したことを教えてくれました。
もちろん、学校の教える読み書きでも、芸術分野でも花開かなくとも、別の分野があるということだと思っていました。
最近、自分が生徒を教えていて思うことは、どうも違うような気がしています。
以下 自分の意見です
× 子どもはなんでもできる可能性があるのに大人がそれを邪魔している
○ 既存の読み書き中心の学校教育に合わない生徒は、芸術工芸分野か科学分野で秀でていることがある
ロンドンでの出張で、「読み書きに問題のある生徒が5人に1人と多い」という話を聞いてきました。読み書き障害(ディスレクシア)というものです。日本では調べられていないので、まだそうした障害なのか、それとも本人がやる気がないのか、それとも教育の機会がなかったのかは、わかりません。
面白いのは、そのディスレクシアの生徒たちは、「読み書きに大きな問題を抱えるにも関わらず、知能レベルは一般と同じで、特に芸術や科学の分野では他の生徒よりも成績が良いことが多い」という報告が多いことです。
ケン・ロビンソンは、誰でもどんな可能性もあると一つの例を出しましたが、もっと限定的なことなのではないかという気がしているというのは、上記のような生徒がいると想定されるからです。日本だと、10人に1人かもしれません。それでも、その生徒たちにとっては、自分が最も苦手なことをずっと耐えなければいけないのです。
ボードゲームは、こうした生徒たちに違った才能を発揮してもらうチャンスだと思っています。
それほど文字に頼らずに、「物事を筋道だてて考えること」「人とコミュニケーションすること」を考えるからです。少なくとも、学校の授業とは別の枠で友達と一緒に過ごすきっかけをくれます。成績のいい子が強いゲームがあってもいいし、成績が低い子が、成績のいい子に勝つようなものがあってもいい。
最後に、ケン・ロビンソンの「教育に革命を!」から以下を引用します。
本当に難しいのは 教育を 根本的に改革することです 改革は難しいものです それはみんなが簡単だと思っていないことを しなければならないからです それは 私達が当然と思うもの 明白だと思うことに 挑戦することになります 改善や変革において 大きな問題になるのは 「常識」という とてつもなく強い力です 常識とは「ずっとそうやってきたんだから 他のやり方はない」と皆が思い込んでいることです。


デジタルパンフレット
学校案内パンフレットを今すぐWebでチェック!