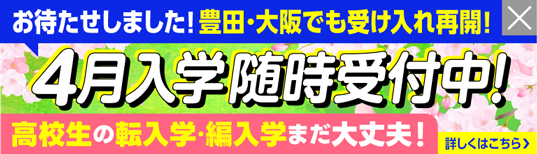新緑にバエる美しい高徳寺山門
2021年05月24日
新緑にバエる美しい高徳寺山門
ルネサンス高校の近くに、以前に紹介した慈雲寺のほかに、大きなお寺がもう一つあります。
そのお寺は高徳寺といいます。鳳林山阿弥陀院と称し、永正元年(1504)の創建(「開基帳」)されたお寺です。

現在の本尊は釈迦如来ですが、阿弥陀院という院号から推して、もとは阿弥陀如来を本尊とする天台系の寺であったとも考えられます。(慈雲寺は弘法大師空海さんの真言系だったのに対して、こちらは伝教大師最澄さんの天台系です。)
寺伝によると、永禄6年(1563)に荒蒔駿河守の外護により、茨城県常陸太田市の耕山寺12世の舜霊文芸が中興したといいます。耕山寺は越後系の曹洞宗であるから、高徳寺も恐らくその際に曹洞宗に改宗したものと思われます。
※ 荒蒔駿河守とは、この大子地方を戦国時代に支配するようになった佐竹氏の家臣です。
・大子町の歴史 ~白川結城氏の支配から佐竹氏の支配へ~
大子町文化遺産 月居城
大子町文化遺産 町付城
講釈はやめて、早速訪ねてみましょう。

いきなり美しい山門です。

山門は、間口3.46メートル、奥行3.52メートル、木造芽葺きで、柱は4本のけやき丸柱で組立てられています。
軒たるきのそり方や軒の方へきて太くなる木鼻のふくらみは室町末期的で、この時代の特徴を示しています。この軒たるきは、東西南北各7本で、そりが優美であり、はまぐりちょうなを使用しています。木鼻は獅子あるいは貘とみられるもので、佐竹時代の特徴の一つと推定されます。肘木や斗の曲線からも時代を知ることができます。
彩色は模様の痕跡からみて全体に施されていたものと推定され、優美さを求めた一人の大工がこつこつ造ったものと思われます。
建築そのものは、素朴単純であるが、美術工芸的な点よりもむしろ、建築様式上歴史的に地方色豊かなもので室町末期(佐竹時代)の建築の特色を有し、文化史的な価値が高いといえます。
本堂はこんな感じです。



鐘楼堂も立派です。

やっぱり山門が美しいです。

見とれます。

因みにこの山門の藁葺屋根は十年に一度、葺き替えをするそうで、それが今年の七月とのこと。作業過程の見学、そして新調された姿を拝観するのもが楽しみです。

また、このお寺には、涅槃図というものがあるそうです。
・大子町文化遺産 涅槃図 http://www.daigo-bunkaisan.jp/page/page000017.html
涅槃図とは、仏教の開祖釈迦(釈尊, ゴータマ・シッダールタ)が沙羅双樹 (さらそうじゅ) の下で入滅(にゅうめつ:お亡くなりになること)する情景を描いた図です。毎年、2月15日の涅槃会(ねはんえ)の時に公開されてみることができるようです。こちらも楽しみです。
- 涅槃会とは、涅槃講や涅槃忌ともいわれ、お釈迦様が入滅されたとされる陰暦の2月15日に、日本や中国などで、釈迦の遺徳追慕と報恩のためにおこなわれる法要(ほうよう:供養するために行われる正式な仏教行事)です。ほかのお寺などでは3月15日に行なわれているところもあるようです。
秋もきれいそうです。→「茨城見聞録」
ルネ高の周りは、歴史や自然の好きな方の楽しみで溢れています。

高徳寺
大子町指定 有形文化財 指定年月日:昭和56年5月19日
所在地:茨城県久慈郡大子町大字上郷2056
この記事の「学校・キャンパス」のページを見る
この記事の関連カテゴリー